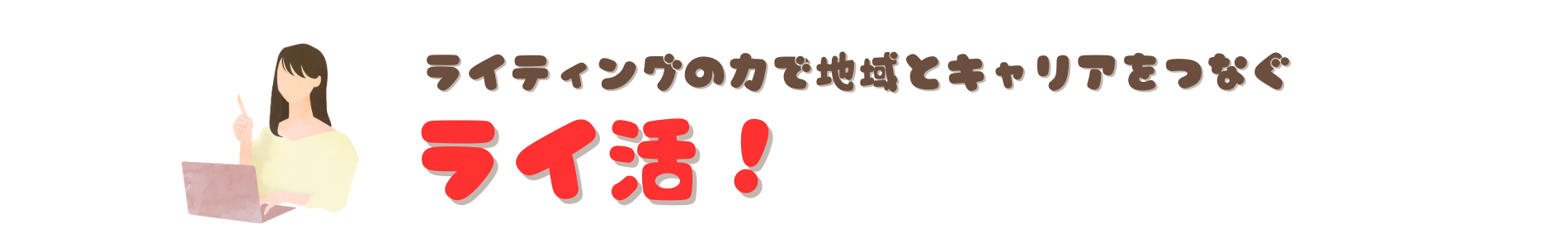子どもの教育費、足りるのかな…。
多くの親御さんが子どもの教育資金への不安を抱えていると思います。
もしも大学までの教育費が無料だったら、もっと子育てに余裕ができると思いませんか?
先日、スウェーデンの講演会に行き、スウェーデンは大学まで教育費が無償だという話を聴きました。
現役の子育て世代の1人としてとても興味深いテーマです。
現在キャリアと結婚や出産との選択に悩んでいる人や、現役子育て世代の人、子持ちのパパママを雇う経営者の方の参考にもなるはずです。
前情報としてスウェーデンの簡単な説明が書いてありますが、スウェーデンについて知っている人や、サクッと読みたい人はぜひ「男女平等社会の取り組み」の部分から見てみてくださいね。
講演会の概要
2025年1月25日(土)山口県山口市地域交流センターで、スウェーデン大使館の外交官ヨハン・フルトクイストさんの講演会が行われました。
講演会の内容は大きく3つに分けると次の通りです。
・スウェーデンの現在の状況
・日本との関わり
・男女平等社会の取り組み
その中でも、スウェーデンの男女平等社会の話については、日本でも講演会の依頼が多いのだそう。
今回、講演でお聞きした内容をもとに、スウェーデンについてまとめてみました。
日本との関係

日本との最初の交流は江戸時代に遡ります。
現代の日本では次のようなものが有名ですね!
- 絵本「長靴下のピッピ」
- アパレルブランド「H&M」
- 家具メーカー「IKEA」
- 車のメーカー「VOLVO」
- スカンジナビアデザイン
 伊藤
伊藤反対に、スウェーデンでは日本のアニメやマンガの文化も入っており、食文化では寿司が人気なのだそうです!
現在VOLVOは現在中国資本になっていますし、こうして見てみると、日本のような世界的な製造業やテクノロジー産業は目立っていないような気がしますね。
スウェーデンの現況


スウェーデンの現在は次のような特徴があります。
・日本と面積が近い
・人口はスウェーデンの方が少ない
・都市部に集中して住んでいる
・SDGsへの意識が高い
・残業がない
・女性の就業率が高い
・税金が高いが、社会保障が手厚い
・子どもの学費が大学まで無料
・待機児童0、子どもたちは1歳からプリスクールに入る
・2023年の一人当たりGDPは15位(日本は34位)
労働時間は日本より短いのに、生産性が落ちず、GDPは日本より上なんですね。
これって不思議だと思いませんか?
どうやって経済成長を維持しつつ、国民の幸せも両立できているのでしょうか?
中国資本になっていますし、こうして見てみると、日本のような世界的な製造業やテクノロジー産業は目立っていないような気がしますね。
男女平等社会への取り組み


2024年の内閣府の調査によるランキングにおいて、スウェーデンは男女平等(ジェンダーギャップ)ランキングで5位という高い順位です。
近年ずっとTOP5にランクインしており、男女平等先進国といえます。



ちなみに、日本は118位。先進国の中ではかなり低い順位です。
現在、スウェーデン大使館には男女平等の講演依頼がとても多いのだとか。講演依頼が来る理由の一つに、これまでのスウェーデンの歩みと現在の日本の状況が似ていることがあげられます。
現在は男女平等で世界的に高水準のスウェーデンですが、実は、20年前まで女性は専業主婦が多く、男性は家事育児をしない人が多かったのです。
スウェーデンの社会で起きた転機
転機は経済成長が停滞したことがきっかけです。
国民全体で経済活動をする必要があり、女性の労働力も求められました。
現在の日本と同様に、社会全体が変わる必要があったのです。
しかし、スウェーデンでは家事育児をしながら働かなければいけない女性たちから反発の声が上がり始めます。
そして働くママたちによる「家事・育児・仕事へのストライキ」が起きました。
働くママたちのストライキの影響


働くママたちのストライキの影響は、社会が変わる大きなきっかけとなりました。
・働き方改革(残業禁止)
・託児所の拡充
・保育士の給与を教員レベルに引き上げ
・男性の育児取得率を上げるため12ヶ月の育児取得のうち2ヶ月を男性の取得として割り当てる
(取得しないと2ヶ月消滅する)
現代の子育て世代にもありがたい政策ばかりですよね。
こうしてスウェーデンの女性たちが声をあげてくれたおかげで現在の男女平等社会があるというわけです。
しかし、女性の社会進出が進むと新たな課題も見えてきました。
スウェーデンの新たな課題
今後の課題は以下の通りです。
・女性のキャリアと妊娠出産の選択
・上場企業では上場企業の役員90%は依然として男性が多い
・アルバイト就労が多い



私自身が働く母親として現役世代なので、とても興味深いテーマでした。
日本とスウェーデンの違い


「残業なし」「6時間勤務」が定着
日本とスウェーデンの働き方で大きく異なる点は、スウェーデンには「残業がない」ということです。
働き方改革で変わってきたとはいえ、企業で働いているとまだまだ忙しいという人も多いですよね。



いまだに「社畜」と言う言葉があるのも、日本ならではという感じ…
企業でクタクタになるまで働き、家では休む暇なく家事育児となると、体調を崩してしまいますよね…。
一方で、スウェーデンでは、そもそも残業という概念がありません。
時間の浪費を減らし、効率よく短時間で仕事をしているのですね。
スウェーデンの子育て事情
スウェーデンでは、待機児童0で、一歳から全員プリスクールに入所できるなど、広い受け皿があります。
家庭では、残業がなく、16時には仕事が終わり、16:30には保育園にお迎えに行きます。
ヨハンさんいわく、スウェーデンでは外遊びをすごく大事にしているので、天気の悪い日でも公園に遊びに連れて行っているとのこと。
公園はパパがたくさんいて、毎日通ううちにパパ友になりカフェに行ったりすることもあるのだそうです!
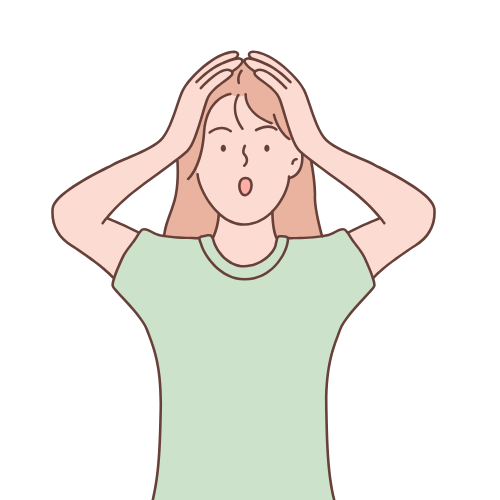
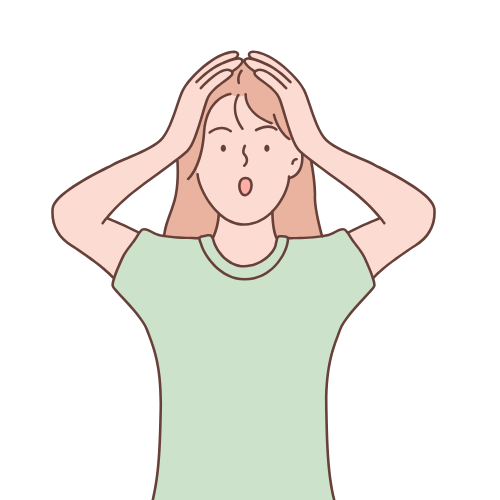
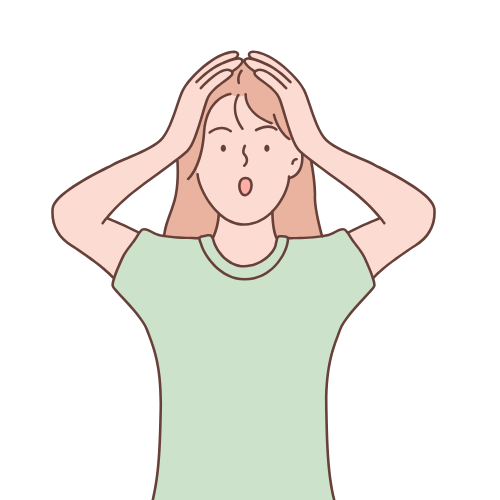
なんて素敵なの!!
さらに驚いたのは、スウェーデンでは時短家電をあまり使うことがないのだそう。
その理由には、残業がないことが関係しています。
一方で日本の共働き世帯の一例として、わが家の場合を例にあげると、夫婦共に時間に追われており、コスパ・タイパが命綱です。



休日はなるべく公園に行くようにはしていますが、仕事が忙しい時などには、時短家電やYouTubeやゲーム、宅配などを活用することも…。
私は子どもと過ごす時間は減らしたくなかったので、ワークライフバランスを整えやすいフリーランスの仕事をしています。
それでもやはり、自身のキャパシティの少なさゆえ、子どもに向き合えていないことに申し訳なさを感じ、苦しくなることはあるので、色々と考えさせられました。
その理由は残業がないから時短する必要ないんだ。ということです。
たしかに残業がなくなれば自由に使える時間は増えます。
では、日本でも残業がなくなれば、子どもとの時間が増え、生活が充実するのでしょうか?
自由時間の使い方
残業が減らない日本では、時短家電があります。
みなさんは、時短家電を使うことでできた時間で何をしてますか?
他の家事をしたり、仕事をしたり、子どもと過ごす時間につかうこともあるし、なくてはならない存在ですよね。
私もそうです。でも私の場合は、ついつい家にいると横になってSNSやYouTubeなんかをダラダラ見ながら体を休めていることも多いです。
休養も大事ですが、ダラダラした時間が多くなってしまうと、せっかく時短家電を使って時間を作っても有効に時間が使えているとはいえないですよね…。
「テクノロジーやお金で可処分時間を増やせた」というだけで、満足してしまっているのかもしれません。
その点、スウェーデンの場合は外に出て遊ぶので、自然と子どもと向き合いやすくなります。
「太陽が出ているうちに家に帰れる」ということにはやはり意味があるように思えてきます。
日本の未来のためにできること
特に子育て世代としては、自分たちだけでなく子どもたちが活きていく未来、次世代がどうすれば満足な収入と理想の生活が両立できるかを考え、不足しているところは声を出して社会そのものを変えていくということが必要なのかもしれません。
私自身、これまでは自分と社会の価値観を変えていき、人生を豊かにするという発想は全くありませんでした。
自分が声をあげるのは面倒なので「誰かがやってくれればいいな」なんて思っていたんですよね。
でも、今回講演会を聞いてみて棚からぼたもちを待っているだけでは何も変わらないということに気づかされました。
教育無償化や働き方改革をしてみて、日本にどのような影響があるかはわかりません。
スウェーデンではこれだけ制度を整えていても実際「出生率は上がっていない」という結果もあります。
でも、やらないよりはやってみる価値があると思いませんか?
まとめ


今回講演してくださったスウェーデン大使館の外交官ヨハン・フルトクイストさんは日本以外にもアジア地区で21年間外交官を務められていながらも、スウェーデンに子どもがいるパパでもあります。
講演中ヨハンさんの言葉で印象的だったのが
「大事なのは、何か違うと思った時には声をあげること」
という言葉です。
個人で声を上げても、社会を変えることは難しいかもしれない。
でも、たくさんの小さな声を集めれば、スウェーデンのように大きな声になり社会が変わることもあるのですね。
・疑問に思ったら同じような立場の人に話してみる
・コスパ、タイパも必要だけど、できた時間で向き合う時間を大切に
・時には自然の中での遊びを取り入れてみる
・家事を頑張りすぎない
・SNSやnoteなどで「声」をあげていく
個人から社会へ、まずはできることから、スウェーデン流の良いところは取り入れていけるといいなと思います。